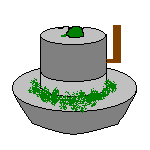
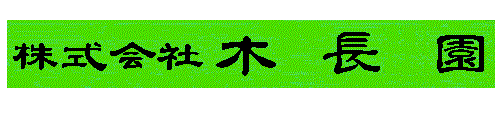
TEL 0774-88-2713
FAX 0774-88-4388
お問い合わせ
ENGLISH
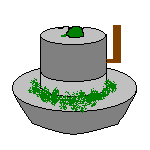
|
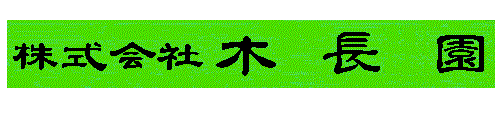
|
TEL 0774-88-2713 FAX 0774-88-4388 お問い合わせ ENGLISH |
||||
| |
|
家庭で茶を作ってみよう |
|
|
||
| |
このページの内容は、ホームページ作者が自身の庭の茶で新茶時、作ってみた試行錯誤の結果です。 あくまでも参考にして頂く程度の内容です。しかし、緑茶、紅茶の違いをご理解いただけると思います。 生の葉っぱが手にはいるかが問題ですけれど、もし手に入ったら是非やってみて下さい。 |
|||||
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2003年の自作茶 |
ウーロン茶を作りました |
|
||
| |
|
2004年の自作茶 |
ウーロン茶のつもりが紅茶に |
|
|
|
| |
|
2005年の自作茶 |
今年はしっかりとウーロン茶 |
|
|
|
| |
|
2006年の自作茶 |
ウーロン茶は今年で最後 |
|
|
|
|
|
||||||
| |
茶の種類 |
ウーロン茶 |
紅 茶 |
煎 茶 |
抹 茶 |
|
| |
作る難易度 |
小 |
小 |
大 |
大 |
|
| |
難易度:茶の品質を問わず、使う道具や作業のしやすさの目安です。 |
|
||||
| |
|
|
|
|
|
|
| ウーロン茶 |
||||||
| 必要な道具 |
新聞紙 台所用手袋かポリ袋 フライパン ドライヤー |
|||||
| 注意点 |
5)と7)のフライパンで酸化を止めるタイミングと、焦がすとほうじ茶になってしまうこと。 |
|||||
| 1)生の葉っぱを、広げた新聞紙にあまり重ならないようにして日光に当てる。 |
||||||
| 2)15分ごとに混ぜること3回。 |
||||||
| 3)室内に入れて、約3時間撹拌を繰り返す。 |
||||||
| 4)萎凋が進み葉の周辺が赤くなり芳香がしてくる。 |
||||||
| 5)酸化を止めるためにフライパンで炒る。焦がさない様注意をすること。しんなりとするのが頃合い。 |
||||||
| 6)手袋をするかポリ袋に入れて、丸めたり押したりして充分に揉む。 少々ちぎれても構わないので15分ほど揉む。もちろん素手でやってもいい。 |
||||||
| 7)再びフライパンで乾燥をする。弱火にして焦がさない様注意。 |
||||||
| 8)あらかた乾燥させれば、後はドライヤーを使用して完全に乾かして完成。 |
||||||
| 紅 茶 |
||||||
| 必要な道具 |
新聞紙 台所用手袋かポリ袋 フライパン ドライヤー |
|||||
| 注意点 |
7)のフライパンで酸化を止めるタイミングと、焦がすとほうじ茶になってしまうこと |
|||||
| 1)生の葉っぱを、広げた新聞紙にあまり重ならないようにして日光に当てる。
|
||||||
| 2)15分ごとに混ぜること3回。 |
||||||
| 3)室内に入れて、茎を曲げても折れなくなるまで、そのまま萎びさせる。約1時間必要。 |
||||||
| 4)萎びたら、手袋をするかポリ袋に入れて、丸めたり押したりして充分に揉む。 少々ちぎれても構わないので15分ほど揉む。充分もめたら新聞紙に広げる。もちろん素手でやってもいい。 |
||||||
| 5)20分ほどで酸化が急激に始まるので、良い香りが部屋中に漂い始める。 |
||||||
| 6)葉っぱの半分ほどが赤くなれば紅茶になる。完全に赤くしてしまうと全然おいしくない。 |
||||||
| 7)酸化を止めるためにフライパンで炒る。焦がさない様注意をしながらあらかた水分を取る。 |
||||||
| 8)あとはドライヤーで乾燥させて出来上がり。茎は乾きにくいので取り除いても良い。 |
||||||
| 煎 茶 |
||||||
| 必要な道具 |
鍋 ざる ホットプレート ドライヤー |
|||||
| 注意点 |
十分に揉み込む事と素早い乾燥。 やけどに注意! |
|||||
| 1)工場なら蒸しますが家庭では面倒なのでゆでます。鍋に沸騰したお湯を沸かし、ざるを使って30秒ゆでる。 |
||||||
| 2)葉っぱ表面の水気をふきんやタオル等で取ります。 |
||||||
| 3)温度60度くらいに設定したホットプレートの上で押したり揉んだりする。 5分揉んでは10分プレート上に広げて乾かす。成分が溶け出しやすくする為です。 |
||||||
| 4)葉の周辺が乾いてくるまで3)を繰り返す。ドライヤーをあてる事も必要。 |
||||||
| 5)細くなるよう手のひらをこすり合わせるようにして形を整える。 |
||||||
| 6)ホットプレート上でドライヤーを当てながら乾燥させて出来上がりです。 |
||||||
| 抹 茶 |
||||||
| 必要な道具 |
鍋 ステンレス製ざる ガスコンロ ホットプレート ドライヤー 厚手の紙 石臼 |
|||||
| |
注意点 |
なんと言っても石臼がネックです。 煎茶と違って揉むことはありません。 |
|
|||
| 1)工場なら蒸しますが家庭では面倒なのでゆでます。葉っぱだけを使います。茎はあらかじめ取り除いておきます。 鍋に沸騰したお湯を沸かし、ざるを使って30秒ゆでる。 |
||||||
| 2)葉っぱ表面の水気をふきんやタオル等で取ります。 |
||||||
| 3)ざるに入れ中火にしたガスコンロの上で焦がさないよう注意しながら荒乾燥させる。 |
||||||
| 4)温度60度くらいに設定したホットプレートの上でドライヤーを当てながら乾燥させる。 パリパリになれば碾茶の完成です。湿らないよう保存すれば以後の行程は別の日でも良い。 |
||||||
| 5)乾燥した葉をざるに入れ、手でこすり合わせて5ミリ角位に細かくする。 |
||||||
| |
6)厚手の紙の先端に載せ両手で持ちパタンパタンと踊らせる様にして葉を吹き飛ばす。 葉脈部分や茎を取り除く作業です。 |
|
||||
| |
7)葉っぱを石臼で挽いて出来上がり。 |
|
||||
| |
|
|
|
|
|
|
| 編集後記 |
庭の茶の木は2m程の幅に植えてあり、5月の連休ごろ手で摘んでいました。300g程収穫します。 まったく肥料をやっていませんので、煎茶や抹茶にするととても渋くて1回作ってみただけです。 この渋みが逆に紅茶やウーロン茶にすると独特のよい香気に変わるので、毎年挑戦していました。 どうしても酸化lさせすぎてしまいます。 なお、生の茶300gから60gのお茶になります。240gは水分です。品種はヤブキタです。 現在は駐車場にしてしまい充分な茶の木がなくなってしまいました。 先日中国四川省の知人から贈られた、すこし開いた芯だけで出来ている高級茶を飲んで驚きました。 文春新書「中国茶図鑑」によれば、蒙頂黄芽の仲間らしい。 毎年作っていた烏龍茶とまったく同じ味香りがしたのです。 残っていた2006年烏龍茶と飲み比べてみると、なんと自作茶のほうが枯れた味がして深みがある、と感じました。 結論、作りたては本物の茶も自作の茶も同じ味香りがした事と、作り方は間違っていなかった。 そして、烏龍茶は熟成させた方が良いのではという事。2011年5月18日 |
|||||
| |
|
|
|
|
|
|